2008年06月10日
『きよしこ』
昨日のこと。
うちの子が「お父さんが貸してくれた本読み終わったから、次の本を貸して」と言ってきました。
もともと、あまり読書好きではなかったのを、「これ、読んでみたら」と奨めたのが、重松清著 『きよしこ』(新潮文庫、今ここに同書がないので頁数・定価は不明)です。
重松清氏の小説は、10冊弱ほど読んでいますが、多くが小学生・中学生を主人公とした作品であり、子どもも共感する部分があるのでは、と思って奨めました。
『きよしこ』は、どもりに悩む少年の、小学生から中学生に至るまでの成長を、冒険や友情、恋などテーマに綴る短編の連作です。おそらくは、筆者自身の実体験が基になっているのだろうと推察しています。
子どものみならず、大人が読んでも、どこか思い当たる節のある、どこか懐かしさを覚える作品ではないでしょうか。
ちなみに、重松清氏の作品は、最近、中学入試問題で扱われることも多いようですので、中学受験をお考えの方は要注意の作家と言えるかもしれません。
もちろん、受験を抜きにしても、重松氏はお奨めできる作家です。
さて、この『きよしこ』の次に、私がうちの子に渡した本は・・・・・・それはまた次の機会に。
うちの子が「お父さんが貸してくれた本読み終わったから、次の本を貸して」と言ってきました。
もともと、あまり読書好きではなかったのを、「これ、読んでみたら」と奨めたのが、重松清著 『きよしこ』(新潮文庫、今ここに同書がないので頁数・定価は不明)です。
重松清氏の小説は、10冊弱ほど読んでいますが、多くが小学生・中学生を主人公とした作品であり、子どもも共感する部分があるのでは、と思って奨めました。
『きよしこ』は、どもりに悩む少年の、小学生から中学生に至るまでの成長を、冒険や友情、恋などテーマに綴る短編の連作です。おそらくは、筆者自身の実体験が基になっているのだろうと推察しています。
子どものみならず、大人が読んでも、どこか思い当たる節のある、どこか懐かしさを覚える作品ではないでしょうか。
ちなみに、重松清氏の作品は、最近、中学入試問題で扱われることも多いようですので、中学受験をお考えの方は要注意の作家と言えるかもしれません。
もちろん、受験を抜きにしても、重松氏はお奨めできる作家です。
さて、この『きよしこ』の次に、私がうちの子に渡した本は・・・・・・それはまた次の機会に。
2008年06月09日
いよいよサナギに・・・・・・
ときどき、話題にする我が家のカブトムシですが、いよいよサナギ化の段階に入っています。
飼育槽の壁際に縦に長い楕円形の部屋を作り、幼虫も頭を上に立った状態で身を固めています。
これからおよそ3~4週間で成虫に。
卵から成虫まで育て上げるのは初めてなので、楽しみです。
親になった気分ですね(すでに人の親ではありますが)。
飼育槽の壁際に縦に長い楕円形の部屋を作り、幼虫も頭を上に立った状態で身を固めています。
これからおよそ3~4週間で成虫に。
卵から成虫まで育て上げるのは初めてなので、楽しみです。
親になった気分ですね(すでに人の親ではありますが)。
2008年06月09日
最近気になるもの
街を散策中、軒下に目がいってしまいます。
そこに何があるか、と申しますと・・・・・・

ツバメの巣、です。この巣では、親鳥がじっと動かず、抱卵中のようでした。

この巣は、割と最近作り直された巣です。同じ場所にあった前代の巣は何らかの原因で崩壊しており、家主の方が崩落防止の板を壁に取り付けてくれています。こちらも抱卵中のようでしたが、親鳥と目が合ったあと、彼女(彼?)は一旦巣から飛び去っていきました。

こちらの巣ではヒナ鳥がかなり成長していました。全部で4羽はいましたが、顔を隠してしまいましたね。撮影後、場所をちょっと離れたら、親鳥がエサを与えに来ました。
写真に撮った以外にも、いくつものツバメの巣を見ましたが、気配を感じない巣が多かったですね。1回目の営巣を終えて、ヒナが巣立っていった後なのかもしれません。
それにしても、今年に限ってどうしてこうもツバメが気になるのか、不思議です。
そこに何があるか、と申しますと・・・・・・
ツバメの巣、です。この巣では、親鳥がじっと動かず、抱卵中のようでした。
この巣は、割と最近作り直された巣です。同じ場所にあった前代の巣は何らかの原因で崩壊しており、家主の方が崩落防止の板を壁に取り付けてくれています。こちらも抱卵中のようでしたが、親鳥と目が合ったあと、彼女(彼?)は一旦巣から飛び去っていきました。
こちらの巣ではヒナ鳥がかなり成長していました。全部で4羽はいましたが、顔を隠してしまいましたね。撮影後、場所をちょっと離れたら、親鳥がエサを与えに来ました。
写真に撮った以外にも、いくつものツバメの巣を見ましたが、気配を感じない巣が多かったですね。1回目の営巣を終えて、ヒナが巣立っていった後なのかもしれません。
それにしても、今年に限ってどうしてこうもツバメが気になるのか、不思議です。
2008年06月08日
初夏の休日
 初夏の遊歩道をウォーキング中です。
初夏の遊歩道をウォーキング中です。モンシロチョウがあちらこちらで舞っています。
巣立ちしたばかりの子雀が、覚束ない足取りで桜の枝を伝ってもいました。
Posted by マンボウくん at
11:51
│Comments(0)
2008年06月07日
『ジャンプ』
先日、佐藤正午氏の『ビコーズ』『リボルバー』について触れましたが、同氏の作品は、この2作の直後に『王様の結婚』(集英社文庫、233頁、本体価格320円[1988年当時])を読了してからのち、久しく手に取ることがありませんでした。
そこから13年後の2001年9月に買ったのが、『スペインの雨』(光文社文庫、287頁、本体価格495円)です。
カバーに記された紹介文には「甘く苦い青春の終わりを噛みしめる9編の短編小説集」とあります。
一編一編の内容はあまり覚えていませんが、読後感がよかったのだと思います。この1冊を機に、それから1年内に10冊以上、佐藤正午氏の文庫を読みました。
その中で、個人的に最も完成度が高いとみているのが、『ジャンプ』(光文社文庫、360頁、本体価格590円)です。
コンビニにリンゴを買いに行ったまま姿を消した彼女。「なぜ彼女は失踪したのか。」 その答えと彼女を探す主人公。
何気ない出来事が、人の人生を大きく変える。コントロールできるようでできない、人生の不可思議さを巧みに描いた『ジャンプ』。
もう少し、上手い表現で伝えられればよいでのすが、その技量がないのが口惜しいですね。
ともあれ、佐藤正午著『ジャンプ』、お奨めの1冊です。

そこから13年後の2001年9月に買ったのが、『スペインの雨』(光文社文庫、287頁、本体価格495円)です。
カバーに記された紹介文には「甘く苦い青春の終わりを噛みしめる9編の短編小説集」とあります。
一編一編の内容はあまり覚えていませんが、読後感がよかったのだと思います。この1冊を機に、それから1年内に10冊以上、佐藤正午氏の文庫を読みました。
その中で、個人的に最も完成度が高いとみているのが、『ジャンプ』(光文社文庫、360頁、本体価格590円)です。
コンビニにリンゴを買いに行ったまま姿を消した彼女。「なぜ彼女は失踪したのか。」 その答えと彼女を探す主人公。
何気ない出来事が、人の人生を大きく変える。コントロールできるようでできない、人生の不可思議さを巧みに描いた『ジャンプ』。
もう少し、上手い表現で伝えられればよいでのすが、その技量がないのが口惜しいですね。
ともあれ、佐藤正午著『ジャンプ』、お奨めの1冊です。
2008年06月06日
ユースホステルの思い出
今日の昼休み。マンボウくん2号との雑談しているうちに、なぜかユースホステルの話題になりました。
「ユースホステルって何ですか」と尋ねる2号くん。数年前まで学生だったはずなのに、どうやらユースホステルを利用したことはない様子。
「ユースホステルというのはね、ヨーロッパを発祥とする、安価で泊まれる宿泊施設で、主に若者を対象にしていて・・・・・・・」と、2号くんに懇々と“ユースホステルとは何ぞや”を説く私。
「そんな宿があったんですね。食事つきで一泊4,000円なら、安いですよね。知らなかったなぁ」とうなずく2号くんです。
話題になったついでに、ネットでユースホステル協会のホームページにもアクセスしました。
「学生時代、ツーリングでよく利用したよなぁ」と、各地方の地図で利用した覚えのあるユースホステルを探しました。
中には「確かここにあったはずなのに・・・」地図上にその名がないYHも。以前に比べると、利用者が減っているという話は聞いていましたので、おそらく廃業したところも少なくはないのでしょう。
もちろん、今でも続いているYHもたくさんあり、ホームページで写真を見ると、「あぁ、ここ行ったよなぁ」と当時の記憶が蘇ります。
旅行での利用ではなかったのですが、一番よく利用したのは、東京飯田橋の東京国際YH。
都か区のビルの20階ぐらいにあって、YHであってYHらしくないYHでした。就職活動で上京する時は真っ先に予約していましたが、満室で泊まれないこともあり、その時は代々木のYHに行ったことも。代々木のYHは東京オリンピックの選手村の宿泊施設を転用したもので、当時すでに古びた観がありましたね。
代々木では、相部屋6人中、4人が外国人だったこともありました。カタコトの英語でコミュニケーションをとったのも、いい思い出です。
東京国際YHに戻ります。
東京国際YHは、当時として珍しく、お酒が飲めるYHで、同泊で、やはり就職活動をしたいた方たちとビールを飲みながら語り合っていましたね。就職活動の合間に、宮本輝氏の『錦繍』を読了したのも、東京国際YHでした。
この『錦繍』は、私にとって初宮本輝作品で、同氏の小説を愛読するきっかけとなった作品です。『錦繍』は、当ブログでも昨年の秋頃に一度取り上げたことがあったと思います。
東京国際YH、いやぁ、思い出すと懐かしいですね。また泊まってみたくなりました。
「ユースホステルって何ですか」と尋ねる2号くん。数年前まで学生だったはずなのに、どうやらユースホステルを利用したことはない様子。
「ユースホステルというのはね、ヨーロッパを発祥とする、安価で泊まれる宿泊施設で、主に若者を対象にしていて・・・・・・・」と、2号くんに懇々と“ユースホステルとは何ぞや”を説く私。
「そんな宿があったんですね。食事つきで一泊4,000円なら、安いですよね。知らなかったなぁ」とうなずく2号くんです。
話題になったついでに、ネットでユースホステル協会のホームページにもアクセスしました。
「学生時代、ツーリングでよく利用したよなぁ」と、各地方の地図で利用した覚えのあるユースホステルを探しました。
中には「確かここにあったはずなのに・・・」地図上にその名がないYHも。以前に比べると、利用者が減っているという話は聞いていましたので、おそらく廃業したところも少なくはないのでしょう。
もちろん、今でも続いているYHもたくさんあり、ホームページで写真を見ると、「あぁ、ここ行ったよなぁ」と当時の記憶が蘇ります。
旅行での利用ではなかったのですが、一番よく利用したのは、東京飯田橋の東京国際YH。
都か区のビルの20階ぐらいにあって、YHであってYHらしくないYHでした。就職活動で上京する時は真っ先に予約していましたが、満室で泊まれないこともあり、その時は代々木のYHに行ったことも。代々木のYHは東京オリンピックの選手村の宿泊施設を転用したもので、当時すでに古びた観がありましたね。
代々木では、相部屋6人中、4人が外国人だったこともありました。カタコトの英語でコミュニケーションをとったのも、いい思い出です。
東京国際YHに戻ります。
東京国際YHは、当時として珍しく、お酒が飲めるYHで、同泊で、やはり就職活動をしたいた方たちとビールを飲みながら語り合っていましたね。就職活動の合間に、宮本輝氏の『錦繍』を読了したのも、東京国際YHでした。
この『錦繍』は、私にとって初宮本輝作品で、同氏の小説を愛読するきっかけとなった作品です。『錦繍』は、当ブログでも昨年の秋頃に一度取り上げたことがあったと思います。
東京国際YH、いやぁ、思い出すと懐かしいですね。また泊まってみたくなりました。
2008年06月05日
オシム氏・岡田氏・日本代表
昨日、イビチャ・オシム前サッカー日本代表監督が、日本サッカー協会のアドバイザー就任に当たって行った記者会見の模様を、TVで観ました。
脳梗塞で倒れて以来、肉声が流れたのは初めてではないかと思いますが、順調な回復ぶりのように見受けられました。
オシム氏が日本代表監督を退いたことを、私は残念に思っておりました。オシム流サッカーの行く着く先に、どのような日本代表のプレーが生まれるのか、非常に期待しておりましたので。それに、オシム氏の軽妙洒脱で、機知に富む語録も楽しみにしていましたし。
代わって就任した岡田監督も、個人的にはその人柄・姿勢に好印象を持っています。
急遽、オシム氏の後を継ぎ、オシム流の継続と岡田氏自身のスタイルとの、言わば無理をした融合を求めて、かえって苦しむ局面を生んだようにも見えましたが、先日のオマーン戦においては、新聞記事や評論家の弁では、岡田色がかなり前面に出ていたようですね。
フランス大会予選でも、加茂監督更迭で思いもかけず代表監督に就任した岡田武史氏。確か予選を突破したあとの雑誌のインタビュー記事で目にしたと思いますが、彼の言葉で印象に残るものがあります。
「どんな試合であれ、負けていいなんて試合は1試合もない」。
外観に似合わず、強い芯と信念、それにきっと熱いハートを持つ人物であることが、この言葉からも窺えます。
南アフリカ大会に向けたワールドカップ予選は、まだ序盤とも言える段階。
岡田監督の下、日本代表はチームとしてのまとまり・成熟を進め、3次予選・最終予選を突破して、4大会連続の出場を果たしてほしいと願っています。
いつもTV観戦ですが、応援していますヨ!
脳梗塞で倒れて以来、肉声が流れたのは初めてではないかと思いますが、順調な回復ぶりのように見受けられました。
オシム氏が日本代表監督を退いたことを、私は残念に思っておりました。オシム流サッカーの行く着く先に、どのような日本代表のプレーが生まれるのか、非常に期待しておりましたので。それに、オシム氏の軽妙洒脱で、機知に富む語録も楽しみにしていましたし。
代わって就任した岡田監督も、個人的にはその人柄・姿勢に好印象を持っています。
急遽、オシム氏の後を継ぎ、オシム流の継続と岡田氏自身のスタイルとの、言わば無理をした融合を求めて、かえって苦しむ局面を生んだようにも見えましたが、先日のオマーン戦においては、新聞記事や評論家の弁では、岡田色がかなり前面に出ていたようですね。
フランス大会予選でも、加茂監督更迭で思いもかけず代表監督に就任した岡田武史氏。確か予選を突破したあとの雑誌のインタビュー記事で目にしたと思いますが、彼の言葉で印象に残るものがあります。
「どんな試合であれ、負けていいなんて試合は1試合もない」。
外観に似合わず、強い芯と信念、それにきっと熱いハートを持つ人物であることが、この言葉からも窺えます。
南アフリカ大会に向けたワールドカップ予選は、まだ序盤とも言える段階。
岡田監督の下、日本代表はチームとしてのまとまり・成熟を進め、3次予選・最終予選を突破して、4大会連続の出場を果たしてほしいと願っています。
いつもTV観戦ですが、応援していますヨ!
2008年06月04日
『リボルバー』
佐藤正午著 『リボルバー』(集英社文庫・268頁)

巻末に記したメモによると、1988年5月28日読了(ほぼ20年前!)。
佐藤正午氏の本は、この2週間ほど前に『ビコーズ』(光文社文庫・323頁)を読了しているので、何か感じるところがあって、続いて同氏の作品を手に取ったのでしょう。
『ビコーズ』の方はすっかり内容を忘れていましたが、『リボルバー』は強い印象とともに、その名を記憶に留めています。
題名となる“リボルバー”すなわち回転弾倉式拳銃をふとしたことから手にした少年を主人公とする本作品。少年が拳銃の使い方を本で調べる場面を、「そんなことするかなぁ」と言ったあと、何も知らなければそうするかも、と思い直しましたね。
長崎出身で、競輪好きの佐藤正午氏。その後、しばらくご無沙汰していましたが、ミレニアムを迎える頃に再び読むようになりました。そのあたりは、またいずれ。
巻末に記したメモによると、1988年5月28日読了(ほぼ20年前!)。
佐藤正午氏の本は、この2週間ほど前に『ビコーズ』(光文社文庫・323頁)を読了しているので、何か感じるところがあって、続いて同氏の作品を手に取ったのでしょう。
『ビコーズ』の方はすっかり内容を忘れていましたが、『リボルバー』は強い印象とともに、その名を記憶に留めています。
題名となる“リボルバー”すなわち回転弾倉式拳銃をふとしたことから手にした少年を主人公とする本作品。少年が拳銃の使い方を本で調べる場面を、「そんなことするかなぁ」と言ったあと、何も知らなければそうするかも、と思い直しましたね。
長崎出身で、競輪好きの佐藤正午氏。その後、しばらくご無沙汰していましたが、ミレニアムを迎える頃に再び読むようになりました。そのあたりは、またいずれ。
2008年06月03日
「樅の木は残った」
今日は、数日前に続き、山本周五郎の作品紹介を。
山本周五郎の代表作と言えば、私は迷わず「樅(もみ)の木は残った」を挙げます。
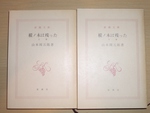
文庫版にして上・下巻計約1,100ページ。読み応えがあります。
題材は、江戸時代前期、17世紀後半の仙台藩で起こった伊達騒動。
山本周五郎は、従来、は騒動の“元凶”と目されていた原田甲斐を主人公に据え、新鮮な視点で伊達騒動を描いています。
歴史解釈にも一石を投げかけたとされるこの「樅の木は残った」。
私が読了したのは1988年11月。
すでに、周五郎作品に魅入られていた私は、満を持してこの作品に取り組みました。
事前に仕入れていた評価に違わず、本作品は私を魅了しました。
構成や表現の巧みさなど、文学的評価は上手く伝えることができないのでやめておきますが、もっとも感動したのは、作家の想像力の深さです。
独自に史料を収集した上での執筆であったと思いますが、「こんな解釈もできるんだ」と驚きました。
事実から推測される真実は見方によって大きく異なることを、本作品で改めて確認しました。
・山本周五郎著 「樅の木は残った」上巻・下巻
新潮文庫:上巻(528頁・本体定価560円[1988年当時])
下巻(594頁・本体定価600円[1988年当時])
山本周五郎の代表作と言えば、私は迷わず「樅(もみ)の木は残った」を挙げます。
文庫版にして上・下巻計約1,100ページ。読み応えがあります。
題材は、江戸時代前期、17世紀後半の仙台藩で起こった伊達騒動。
山本周五郎は、従来、は騒動の“元凶”と目されていた原田甲斐を主人公に据え、新鮮な視点で伊達騒動を描いています。
歴史解釈にも一石を投げかけたとされるこの「樅の木は残った」。
私が読了したのは1988年11月。
すでに、周五郎作品に魅入られていた私は、満を持してこの作品に取り組みました。
事前に仕入れていた評価に違わず、本作品は私を魅了しました。
構成や表現の巧みさなど、文学的評価は上手く伝えることができないのでやめておきますが、もっとも感動したのは、作家の想像力の深さです。
独自に史料を収集した上での執筆であったと思いますが、「こんな解釈もできるんだ」と驚きました。
事実から推測される真実は見方によって大きく異なることを、本作品で改めて確認しました。
・山本周五郎著 「樅の木は残った」上巻・下巻
新潮文庫:上巻(528頁・本体定価560円[1988年当時])
下巻(594頁・本体定価600円[1988年当時])
2008年06月02日
オマーン戦、快勝でした。
今夜行われたサッカー・ワールドカップ、アジア3次予選。対オマーン戦、ホームゲーム。
楽観できないとみていましたが、日本代表は3-0と快勝。早い時間帯に先制、追加点が入っていたので、ハラハラすることなく、安心して観戦(TV)できましたね。
今週末はアウェーで再びオマーンと対戦。今日よりは厳しい戦いになると思われますが、何とか勝ち点3を奪い、続くタイ、バーレーン戦に向けての弾みにしてほしいと願います。
個人的には、今回代表帯同を辞退した高原選手の、いち早い復調を待ち望んでおります。
楽観できないとみていましたが、日本代表は3-0と快勝。早い時間帯に先制、追加点が入っていたので、ハラハラすることなく、安心して観戦(TV)できましたね。
今週末はアウェーで再びオマーンと対戦。今日よりは厳しい戦いになると思われますが、何とか勝ち点3を奪い、続くタイ、バーレーン戦に向けての弾みにしてほしいと願います。
個人的には、今回代表帯同を辞退した高原選手の、いち早い復調を待ち望んでおります。
2008年06月01日
草刈りと読書
今朝は地域の定期清掃に子どもとともに参加。小一時間、公園の草を刈りました。
その流れで、庭の雑草とも格闘約1時間。1ヶ月ほど前にも雑草を抜いたのですが、この季節、植物は生長が早いですね。
その後は、読書を少々。先日、ここでも紹介したあと、眠ってしまって読みかけのままだった村上春樹氏の文庫と、随分前からカバンの奥で眠ったままだった原田宗典氏のエッセイ集とを、2冊続けて読了。
原田氏は、私が好んで読む作家の一人。氏のエッセイは抱腹の作が多いのですが、最近は必ずしもさにあらず、また違う趣の作を世に送り出していますね。
先日、書棚を整理して未読の文庫がたくさん出てきたこともあり、このところ低温状態が続いていた読書熱が、再び上昇局面に移ってきた気がしています。
◆本日の読了書
・村上春樹著『東京奇譚集』
・原田宗典著『私は好奇心の強いゴッドファーザー』(講談社文庫・269頁・本体定価571円)
・・・・・・作者が鑑賞した映画と、それをめぐる作者のエピソード・想い出を語ったエッセイ集。

その流れで、庭の雑草とも格闘約1時間。1ヶ月ほど前にも雑草を抜いたのですが、この季節、植物は生長が早いですね。
その後は、読書を少々。先日、ここでも紹介したあと、眠ってしまって読みかけのままだった村上春樹氏の文庫と、随分前からカバンの奥で眠ったままだった原田宗典氏のエッセイ集とを、2冊続けて読了。
原田氏は、私が好んで読む作家の一人。氏のエッセイは抱腹の作が多いのですが、最近は必ずしもさにあらず、また違う趣の作を世に送り出していますね。
先日、書棚を整理して未読の文庫がたくさん出てきたこともあり、このところ低温状態が続いていた読書熱が、再び上昇局面に移ってきた気がしています。
◆本日の読了書
・村上春樹著『東京奇譚集』
・原田宗典著『私は好奇心の強いゴッドファーザー』(講談社文庫・269頁・本体定価571円)
・・・・・・作者が鑑賞した映画と、それをめぐる作者のエピソード・想い出を語ったエッセイ集。





