2011年09月15日
今夜が遅いのは雑用で。
最近、松本清張の本をちょこちょこ読んでいます。
描かれている時代がちょっと古くはあるのですが、数ページ読むだけで、すでに引き込まれている自分に気付きます。すぐに次の展開に期待を抱かせるというのでしょうか、ページを繰るペースが早めです。
ついつい読み進めてしまうので、就寝が遅くなることも。
清張の作品、魅力あるのですが、ちょっと不満というか残念な点があります。
それは・・・ハッピーエンドが無い、基調は暗め、ということです。
事件モノは、もちろん解決されて、犯人が挙げられるのですが、カタルシスを得られるような終幕ではありません。事件モノ以外でも、『告訴せず』のように主人公が寂しい末路を迎える話がほとんどです。
それがわかっていても、先へ先へ、という気持ちは失せませんけれど。
ともあれ、先日も1冊読了して、次は何を読もうかと、思案&楽しみにしているところです。
描かれている時代がちょっと古くはあるのですが、数ページ読むだけで、すでに引き込まれている自分に気付きます。すぐに次の展開に期待を抱かせるというのでしょうか、ページを繰るペースが早めです。
ついつい読み進めてしまうので、就寝が遅くなることも。
清張の作品、魅力あるのですが、ちょっと不満というか残念な点があります。
それは・・・ハッピーエンドが無い、基調は暗め、ということです。
事件モノは、もちろん解決されて、犯人が挙げられるのですが、カタルシスを得られるような終幕ではありません。事件モノ以外でも、『告訴せず』のように主人公が寂しい末路を迎える話がほとんどです。
それがわかっていても、先へ先へ、という気持ちは失せませんけれど。
ともあれ、先日も1冊読了して、次は何を読もうかと、思案&楽しみにしているところです。
2011年06月21日
選ぶ時間も楽しいです。
また、随分ご無沙汰してしまった当ブログ。
夏至を迎える今頃になって今年初投稿。
まぁ、それはそれ、「そうだったっけ?」と気にせず流して、本題に移りますか。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ここ1ヶ月ほど、以前読んだ本を6、7数冊ほど読み返しています。
「以前」とは、10~20年ほど前です。
読み返して気付くのは、タイトルには見覚えはあるものの、内容に関しては結構記憶の彼方に飛んでしまっているということです。
きっかけは、書棚の1冊をたまたま手にして読み始めたところ、「この話、どう展開したかな?」とそのまま読み進めたことです。
以来、内容にあまり覚えがない本を探しては、読んでいるところです。
なかには、ところどころ傍線を引いている本もあって、「そんなことをしていたっけ?」と全く記憶になくて驚いたりもしています。
奥さんに話すと「記憶力が低下しているんじゃない?」 なんて言われそうな気もしますが、まぁ、既読本をもう一度楽しめる、ということで、前向きに考えたいと思います。
夏至を迎える今頃になって今年初投稿。
まぁ、それはそれ、「そうだったっけ?」と気にせず流して、本題に移りますか。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ここ1ヶ月ほど、以前読んだ本を6、7数冊ほど読み返しています。
「以前」とは、10~20年ほど前です。
読み返して気付くのは、タイトルには見覚えはあるものの、内容に関しては結構記憶の彼方に飛んでしまっているということです。
きっかけは、書棚の1冊をたまたま手にして読み始めたところ、「この話、どう展開したかな?」とそのまま読み進めたことです。
以来、内容にあまり覚えがない本を探しては、読んでいるところです。
なかには、ところどころ傍線を引いている本もあって、「そんなことをしていたっけ?」と全く記憶になくて驚いたりもしています。
奥さんに話すと「記憶力が低下しているんじゃない?」 なんて言われそうな気もしますが、まぁ、既読本をもう一度楽しめる、ということで、前向きに考えたいと思います。
2008年11月17日
重松清『いとしのヒナゴン』
今日は朝から読書。
子どもの「遊ぼう」リクエストも保留にして、読み進めました。
おかげで、昼過ぎに読了。
今回読んでいたのは、重松清氏の『いとしのヒナゴン』(文春文庫/定価:上巻524円、下巻495円)。
舞台は中国地方の山間部の町。
“未確認生物”ヒナゴンをめぐる人々の思いと友情を軸にしつつ、過疎・高齢化が進む地方の政治の混迷がそこに押し寄せます。
泥臭い現実の中のほろ苦さが描かれつつも、全編を通じて、人として信じることの大切さや力が強く訴えられた作品です。
読後感はさわやかさで一杯、とはいかないものの、重松作品らしい、先々の希望が見える終わり方でした。
さすが重松清。好作品です。
子どもの「遊ぼう」リクエストも保留にして、読み進めました。
おかげで、昼過ぎに読了。
今回読んでいたのは、重松清氏の『いとしのヒナゴン』(文春文庫/定価:上巻524円、下巻495円)。
舞台は中国地方の山間部の町。
“未確認生物”ヒナゴンをめぐる人々の思いと友情を軸にしつつ、過疎・高齢化が進む地方の政治の混迷がそこに押し寄せます。
泥臭い現実の中のほろ苦さが描かれつつも、全編を通じて、人として信じることの大切さや力が強く訴えられた作品です。
読後感はさわやかさで一杯、とはいかないものの、重松作品らしい、先々の希望が見える終わり方でした。
さすが重松清。好作品です。
2008年11月15日
久しぶりに読んでいます。
今年は、まったくもって話にならないほどしか、本を読めていません。
まぁ、原因は自覚していますが、まだまだ状況はすぐに変わらないでしょう。
それでも、一度本を手にすると、すぐに次へ次へと読み進めます。
ですが、ある日はちょっと読書できても、翌日はその時間がない、というケースばかり。
今も、週初めに読み始めた文庫を、ようやく5日ぶりに手にしたところ。
この間、続きを読みたい、という気持ちはありましたが、結局、今になってようやく、です。
明日は明日で予定があるので、今夜のうちに読めるだけ読み進めておきます。
まぁ、原因は自覚していますが、まだまだ状況はすぐに変わらないでしょう。
それでも、一度本を手にすると、すぐに次へ次へと読み進めます。
ですが、ある日はちょっと読書できても、翌日はその時間がない、というケースばかり。
今も、週初めに読み始めた文庫を、ようやく5日ぶりに手にしたところ。
この間、続きを読みたい、という気持ちはありましたが、結局、今になってようやく、です。
明日は明日で予定があるので、今夜のうちに読めるだけ読み進めておきます。
2008年08月01日
宮部みゆき 『火車』
宮部みゆき著 『火車』(新潮文庫・590ページ・743円<税別。1998年当時>)

新潮社主催の文学賞・山本周五郎賞に輝いた、宮部さんの秀作です。
文庫化されるのを待ち焦がれていた作品で、文庫新刊で購入し、すぐに読了しています(1998年2月)。
「電車が綾瀬の駅を離れたところで、雨が降り始めた。なかば凍った雨だった。どうりで朝から左膝が痛むはずだった。」
書き出しのこの一節。正確なフレーズとしては覚えてはいませんでしたが、なぜか強く印象に残っています。ストーリー全体を暗示するようなこの書き出し。簡単そうで、こうした表現はなかなかできないと感服した記憶があります。
他人になりすました人物を追っていく長編ミステリー。期待を裏切らない力作でした。
今、最近読書がブームになっている my 奥さんが、読んでいます。

新潮社主催の文学賞・山本周五郎賞に輝いた、宮部さんの秀作です。
文庫化されるのを待ち焦がれていた作品で、文庫新刊で購入し、すぐに読了しています(1998年2月)。
「電車が綾瀬の駅を離れたところで、雨が降り始めた。なかば凍った雨だった。どうりで朝から左膝が痛むはずだった。」
書き出しのこの一節。正確なフレーズとしては覚えてはいませんでしたが、なぜか強く印象に残っています。ストーリー全体を暗示するようなこの書き出し。簡単そうで、こうした表現はなかなかできないと感服した記憶があります。
他人になりすました人物を追っていく長編ミステリー。期待を裏切らない力作でした。
今、最近読書がブームになっている my 奥さんが、読んでいます。
2008年06月25日
井上靖『しろばんば』
今日はどうしようか・・・・・・と思いつつ、本棚をのぞいて手にしたのは、井上靖著『しろばんば』(新潮文庫・531頁・560円<1989年読了当時>)。

井上靖さんといえば、昨年のNHK大河ドラマ「風林火山」の原作者ですが、残念ながら私は『風林火山』は読んでいません。本も数冊しか持っていませんが、一番印象に残っているのが『しろばんば』です。
『しろばんば』は伊豆の田舎に暮らす少年の成長の物語。理由は明らかにされていませんでしたが、親とは別に、曽祖父のお妾さんだったお婆さんと二人、土蔵で暮らす少年。
戦前の、自然に満ちた伊豆の山中で、ちょっと特異な環境下で育っていく少年。抑揚は少ないけれど、それだけに少年の心情が素直に胸に入ってきたことを覚えています。
確か、友人に「読んでいないの?」と言われたのがきっかけで手にした1冊だったと思いますが、読んでみてよかったと思える1冊ですね。

井上靖さんといえば、昨年のNHK大河ドラマ「風林火山」の原作者ですが、残念ながら私は『風林火山』は読んでいません。本も数冊しか持っていませんが、一番印象に残っているのが『しろばんば』です。
『しろばんば』は伊豆の田舎に暮らす少年の成長の物語。理由は明らかにされていませんでしたが、親とは別に、曽祖父のお妾さんだったお婆さんと二人、土蔵で暮らす少年。
戦前の、自然に満ちた伊豆の山中で、ちょっと特異な環境下で育っていく少年。抑揚は少ないけれど、それだけに少年の心情が素直に胸に入ってきたことを覚えています。
確か、友人に「読んでいないの?」と言われたのがきっかけで手にした1冊だったと思いますが、読んでみてよかったと思える1冊ですね。
2008年06月18日
『レベル7』
前回の『魔術はささやく』に次いで手にした宮部みゆき作品は、『レベル7』(新潮文庫・665頁・本体価格699円<1993年読了当時>)です。

1993年秋に文庫で新刊で出たのをすぐに購入し、読了しています。
『レベル7』・・・・・・長編のミステリーで、細かい筋は忘却の彼方に去ってしまいましたが、事件の設定から謎が明らかにされる展開まで、緻密に練り上げられた筋に、読了後、思わず「参った」と感嘆したことは、鮮明に覚えています。
ただ、感嘆する作品はこればかりではないのが、宮部みゆきの宮部みゆきたる所以ですね。

1993年秋に文庫で新刊で出たのをすぐに購入し、読了しています。
『レベル7』・・・・・・長編のミステリーで、細かい筋は忘却の彼方に去ってしまいましたが、事件の設定から謎が明らかにされる展開まで、緻密に練り上げられた筋に、読了後、思わず「参った」と感嘆したことは、鮮明に覚えています。
ただ、感嘆する作品はこればかりではないのが、宮部みゆきの宮部みゆきたる所以ですね。
2008年06月17日
『魔術はささやく』
前の投稿で、宮部みゆきさんのことに触れましたが、私が初めて手にした彼女の作品は、『魔術はささやく』(新潮文庫・406頁・本体505円<1993年読了当時>です。

この作品が発表された頃、宮部さんは本格作家デビューしてまだ数年ではなかったかと思いますが、構成、設定、展開の、新人とは思えない出来栄えに驚きました。次は次は、と一気に読み進めました。
この作品を機に、私は宮部作品のファンとなり、およそ40冊、文庫を読み重ねました。
でも、そのうちの1冊は、昨年、読みかけたまま旅立った母といっしょに、彼岸に渡りました。合掌。
この作品が発表された頃、宮部さんは本格作家デビューしてまだ数年ではなかったかと思いますが、構成、設定、展開の、新人とは思えない出来栄えに驚きました。次は次は、と一気に読み進めました。
この作品を機に、私は宮部作品のファンとなり、およそ40冊、文庫を読み重ねました。
でも、そのうちの1冊は、昨年、読みかけたまま旅立った母といっしょに、彼岸に渡りました。合掌。
2008年06月16日
『ステップファザー・ステップ』
先日、子どもが重松清さんの『きよしこ』を読み終えたので、次の本を貸した、と書きました。
その本とは・・・・・・宮部みゆき著『ステップファザー・ステップ』(講談社文庫・360頁・563円<読了時=1996年当時>)。

宮部みゆきさんは、ミステリー・時代物・SFなど幅広いジャンルにおいて作品を上梓し、しかもそれらいずれもが専門とも言えるほど読者を魅了する作品に仕上がっている、当代随一の人気作家の一人です。
彼女の作品を読むにつれ、この作家は、執筆するにあたっては綿密な事前準備・取材・資料収集・調査をしていることが推察されます。
一言で言えば、“多才な作家”と表現できるのかもしれませんが、下地の確かさが窺える、裏切られることの少ない作家と思います。
話を表題の作品に戻しますと、この『ステップファザー・ステップ』は、ちょっと変わった(?)中学生の双子の兄弟と、ひょんなことから彼らの父親代わりをすることになった泥棒、この3人が遭遇する事件を綴る短編連作集です。ちなみに、確か“ステップファザー”とは、“継父”の意味です。
軽妙でユーモアに満ちていて、子どもでも楽しく読める作品、ということで、子どもにも奨めてみました。さて、今度は読み終えるまでにどのくらいかかるでしょうね。
その本とは・・・・・・宮部みゆき著『ステップファザー・ステップ』(講談社文庫・360頁・563円<読了時=1996年当時>)。
宮部みゆきさんは、ミステリー・時代物・SFなど幅広いジャンルにおいて作品を上梓し、しかもそれらいずれもが専門とも言えるほど読者を魅了する作品に仕上がっている、当代随一の人気作家の一人です。
彼女の作品を読むにつれ、この作家は、執筆するにあたっては綿密な事前準備・取材・資料収集・調査をしていることが推察されます。
一言で言えば、“多才な作家”と表現できるのかもしれませんが、下地の確かさが窺える、裏切られることの少ない作家と思います。
話を表題の作品に戻しますと、この『ステップファザー・ステップ』は、ちょっと変わった(?)中学生の双子の兄弟と、ひょんなことから彼らの父親代わりをすることになった泥棒、この3人が遭遇する事件を綴る短編連作集です。ちなみに、確か“ステップファザー”とは、“継父”の意味です。
軽妙でユーモアに満ちていて、子どもでも楽しく読める作品、ということで、子どもにも奨めてみました。さて、今度は読み終えるまでにどのくらいかかるでしょうね。
2008年06月11日
『青が散る』
私が、愛読している、と思っている作家の方は、山本周五郎氏、池波正太郎氏、渡部淳一氏、原田宗典氏、佐藤正午氏、村上春樹氏、宮部みゆき氏、竹内久美子氏等々、10数名ほど名前が挙がりますが、その第一号(?)とも言えるのは、宮本輝氏です。
最近も少し触れた『錦繍』(1988年5月読了)を皮切りに、その頃文庫化されていた作品をかなりのハイペースで読みました。
同氏の長編小説『青が散る』(文春文庫・478頁・本体定価520円<当時>)も、その頃に読んだ1冊です。

芥川賞作家でもある宮本輝氏の作品は、いわゆる純文学的傾向が濃いのですが、大学のテニス部を舞台にした青春小説(と言っていいのかな?)『青が散る』は、肩肘張らずに、“ものがたり”として読むことができた作品でした。
『青が散る』は、石黒賢さん主演でテレビドラマにもなっており、若き日の佐藤浩市さんも出演していたと思います。佐藤浩市さん、最近映画の宣伝でよくテレビに出ていましたが、ホントいい役者さんになりましたね。それに、お父さんにも似てきましたね。
あっ、石黒賢さんはいい役者さんにはなっていない、と言っているわけではありませんよ。念のため・・・・・・。
最近も少し触れた『錦繍』(1988年5月読了)を皮切りに、その頃文庫化されていた作品をかなりのハイペースで読みました。
同氏の長編小説『青が散る』(文春文庫・478頁・本体定価520円<当時>)も、その頃に読んだ1冊です。
芥川賞作家でもある宮本輝氏の作品は、いわゆる純文学的傾向が濃いのですが、大学のテニス部を舞台にした青春小説(と言っていいのかな?)『青が散る』は、肩肘張らずに、“ものがたり”として読むことができた作品でした。
『青が散る』は、石黒賢さん主演でテレビドラマにもなっており、若き日の佐藤浩市さんも出演していたと思います。佐藤浩市さん、最近映画の宣伝でよくテレビに出ていましたが、ホントいい役者さんになりましたね。それに、お父さんにも似てきましたね。
あっ、石黒賢さんはいい役者さんにはなっていない、と言っているわけではありませんよ。念のため・・・・・・。
2008年06月10日
『きよしこ』
昨日のこと。
うちの子が「お父さんが貸してくれた本読み終わったから、次の本を貸して」と言ってきました。
もともと、あまり読書好きではなかったのを、「これ、読んでみたら」と奨めたのが、重松清著 『きよしこ』(新潮文庫、今ここに同書がないので頁数・定価は不明)です。
重松清氏の小説は、10冊弱ほど読んでいますが、多くが小学生・中学生を主人公とした作品であり、子どもも共感する部分があるのでは、と思って奨めました。
『きよしこ』は、どもりに悩む少年の、小学生から中学生に至るまでの成長を、冒険や友情、恋などテーマに綴る短編の連作です。おそらくは、筆者自身の実体験が基になっているのだろうと推察しています。
子どものみならず、大人が読んでも、どこか思い当たる節のある、どこか懐かしさを覚える作品ではないでしょうか。
ちなみに、重松清氏の作品は、最近、中学入試問題で扱われることも多いようですので、中学受験をお考えの方は要注意の作家と言えるかもしれません。
もちろん、受験を抜きにしても、重松氏はお奨めできる作家です。
さて、この『きよしこ』の次に、私がうちの子に渡した本は・・・・・・それはまた次の機会に。
うちの子が「お父さんが貸してくれた本読み終わったから、次の本を貸して」と言ってきました。
もともと、あまり読書好きではなかったのを、「これ、読んでみたら」と奨めたのが、重松清著 『きよしこ』(新潮文庫、今ここに同書がないので頁数・定価は不明)です。
重松清氏の小説は、10冊弱ほど読んでいますが、多くが小学生・中学生を主人公とした作品であり、子どもも共感する部分があるのでは、と思って奨めました。
『きよしこ』は、どもりに悩む少年の、小学生から中学生に至るまでの成長を、冒険や友情、恋などテーマに綴る短編の連作です。おそらくは、筆者自身の実体験が基になっているのだろうと推察しています。
子どものみならず、大人が読んでも、どこか思い当たる節のある、どこか懐かしさを覚える作品ではないでしょうか。
ちなみに、重松清氏の作品は、最近、中学入試問題で扱われることも多いようですので、中学受験をお考えの方は要注意の作家と言えるかもしれません。
もちろん、受験を抜きにしても、重松氏はお奨めできる作家です。
さて、この『きよしこ』の次に、私がうちの子に渡した本は・・・・・・それはまた次の機会に。
2008年06月07日
『ジャンプ』
先日、佐藤正午氏の『ビコーズ』『リボルバー』について触れましたが、同氏の作品は、この2作の直後に『王様の結婚』(集英社文庫、233頁、本体価格320円[1988年当時])を読了してからのち、久しく手に取ることがありませんでした。
そこから13年後の2001年9月に買ったのが、『スペインの雨』(光文社文庫、287頁、本体価格495円)です。
カバーに記された紹介文には「甘く苦い青春の終わりを噛みしめる9編の短編小説集」とあります。
一編一編の内容はあまり覚えていませんが、読後感がよかったのだと思います。この1冊を機に、それから1年内に10冊以上、佐藤正午氏の文庫を読みました。
その中で、個人的に最も完成度が高いとみているのが、『ジャンプ』(光文社文庫、360頁、本体価格590円)です。
コンビニにリンゴを買いに行ったまま姿を消した彼女。「なぜ彼女は失踪したのか。」 その答えと彼女を探す主人公。
何気ない出来事が、人の人生を大きく変える。コントロールできるようでできない、人生の不可思議さを巧みに描いた『ジャンプ』。
もう少し、上手い表現で伝えられればよいでのすが、その技量がないのが口惜しいですね。
ともあれ、佐藤正午著『ジャンプ』、お奨めの1冊です。

そこから13年後の2001年9月に買ったのが、『スペインの雨』(光文社文庫、287頁、本体価格495円)です。
カバーに記された紹介文には「甘く苦い青春の終わりを噛みしめる9編の短編小説集」とあります。
一編一編の内容はあまり覚えていませんが、読後感がよかったのだと思います。この1冊を機に、それから1年内に10冊以上、佐藤正午氏の文庫を読みました。
その中で、個人的に最も完成度が高いとみているのが、『ジャンプ』(光文社文庫、360頁、本体価格590円)です。
コンビニにリンゴを買いに行ったまま姿を消した彼女。「なぜ彼女は失踪したのか。」 その答えと彼女を探す主人公。
何気ない出来事が、人の人生を大きく変える。コントロールできるようでできない、人生の不可思議さを巧みに描いた『ジャンプ』。
もう少し、上手い表現で伝えられればよいでのすが、その技量がないのが口惜しいですね。
ともあれ、佐藤正午著『ジャンプ』、お奨めの1冊です。
2008年06月04日
『リボルバー』
佐藤正午著 『リボルバー』(集英社文庫・268頁)

巻末に記したメモによると、1988年5月28日読了(ほぼ20年前!)。
佐藤正午氏の本は、この2週間ほど前に『ビコーズ』(光文社文庫・323頁)を読了しているので、何か感じるところがあって、続いて同氏の作品を手に取ったのでしょう。
『ビコーズ』の方はすっかり内容を忘れていましたが、『リボルバー』は強い印象とともに、その名を記憶に留めています。
題名となる“リボルバー”すなわち回転弾倉式拳銃をふとしたことから手にした少年を主人公とする本作品。少年が拳銃の使い方を本で調べる場面を、「そんなことするかなぁ」と言ったあと、何も知らなければそうするかも、と思い直しましたね。
長崎出身で、競輪好きの佐藤正午氏。その後、しばらくご無沙汰していましたが、ミレニアムを迎える頃に再び読むようになりました。そのあたりは、またいずれ。
巻末に記したメモによると、1988年5月28日読了(ほぼ20年前!)。
佐藤正午氏の本は、この2週間ほど前に『ビコーズ』(光文社文庫・323頁)を読了しているので、何か感じるところがあって、続いて同氏の作品を手に取ったのでしょう。
『ビコーズ』の方はすっかり内容を忘れていましたが、『リボルバー』は強い印象とともに、その名を記憶に留めています。
題名となる“リボルバー”すなわち回転弾倉式拳銃をふとしたことから手にした少年を主人公とする本作品。少年が拳銃の使い方を本で調べる場面を、「そんなことするかなぁ」と言ったあと、何も知らなければそうするかも、と思い直しましたね。
長崎出身で、競輪好きの佐藤正午氏。その後、しばらくご無沙汰していましたが、ミレニアムを迎える頃に再び読むようになりました。そのあたりは、またいずれ。
2008年06月03日
「樅の木は残った」
今日は、数日前に続き、山本周五郎の作品紹介を。
山本周五郎の代表作と言えば、私は迷わず「樅(もみ)の木は残った」を挙げます。
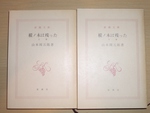
文庫版にして上・下巻計約1,100ページ。読み応えがあります。
題材は、江戸時代前期、17世紀後半の仙台藩で起こった伊達騒動。
山本周五郎は、従来、は騒動の“元凶”と目されていた原田甲斐を主人公に据え、新鮮な視点で伊達騒動を描いています。
歴史解釈にも一石を投げかけたとされるこの「樅の木は残った」。
私が読了したのは1988年11月。
すでに、周五郎作品に魅入られていた私は、満を持してこの作品に取り組みました。
事前に仕入れていた評価に違わず、本作品は私を魅了しました。
構成や表現の巧みさなど、文学的評価は上手く伝えることができないのでやめておきますが、もっとも感動したのは、作家の想像力の深さです。
独自に史料を収集した上での執筆であったと思いますが、「こんな解釈もできるんだ」と驚きました。
事実から推測される真実は見方によって大きく異なることを、本作品で改めて確認しました。
・山本周五郎著 「樅の木は残った」上巻・下巻
新潮文庫:上巻(528頁・本体定価560円[1988年当時])
下巻(594頁・本体定価600円[1988年当時])
山本周五郎の代表作と言えば、私は迷わず「樅(もみ)の木は残った」を挙げます。
文庫版にして上・下巻計約1,100ページ。読み応えがあります。
題材は、江戸時代前期、17世紀後半の仙台藩で起こった伊達騒動。
山本周五郎は、従来、は騒動の“元凶”と目されていた原田甲斐を主人公に据え、新鮮な視点で伊達騒動を描いています。
歴史解釈にも一石を投げかけたとされるこの「樅の木は残った」。
私が読了したのは1988年11月。
すでに、周五郎作品に魅入られていた私は、満を持してこの作品に取り組みました。
事前に仕入れていた評価に違わず、本作品は私を魅了しました。
構成や表現の巧みさなど、文学的評価は上手く伝えることができないのでやめておきますが、もっとも感動したのは、作家の想像力の深さです。
独自に史料を収集した上での執筆であったと思いますが、「こんな解釈もできるんだ」と驚きました。
事実から推測される真実は見方によって大きく異なることを、本作品で改めて確認しました。
・山本周五郎著 「樅の木は残った」上巻・下巻
新潮文庫:上巻(528頁・本体定価560円[1988年当時])
下巻(594頁・本体定価600円[1988年当時])
2008年05月30日
今日の一冊
今日読んでいたのは
村上春樹著 『東京奇譚集』 (新潮文庫 本体定価400円)
タイトルに“奇譚”がつく作品といえば、永井荷風の『墨東奇譚』を思い浮かべますが、こちらは高校生か大学生の頃に読んだものの、話の内容はすっかり忘れました。
閑話休題。
村上春樹作品は、最近はちょっとご無沙汰しており、昨年末に購入したこの本も、“積読”状態でしたが、本日、たまたま手にして読み始めました。
まだ、途中ですが、ついつい引き込まれます。さすが、世界の村上春樹。
タイトル通り、“不思議な出来事”を綴る4作品が収録されています。
冒頭、村上春樹さん自らが語る形で、「過去に僕の身に起こったいくつかの“不思議な出来事”」についての作品と述べ、フィクションではない、と言ってあるのですが、それが本当なのかどうかはわかりません。
ともあれ、これから続きを読んでしまおうと思います。
村上春樹著 『東京奇譚集』 (新潮文庫 本体定価400円)
タイトルに“奇譚”がつく作品といえば、永井荷風の『墨東奇譚』を思い浮かべますが、こちらは高校生か大学生の頃に読んだものの、話の内容はすっかり忘れました。
閑話休題。
村上春樹作品は、最近はちょっとご無沙汰しており、昨年末に購入したこの本も、“積読”状態でしたが、本日、たまたま手にして読み始めました。
まだ、途中ですが、ついつい引き込まれます。さすが、世界の村上春樹。
タイトル通り、“不思議な出来事”を綴る4作品が収録されています。
冒頭、村上春樹さん自らが語る形で、「過去に僕の身に起こったいくつかの“不思議な出来事”」についての作品と述べ、フィクションではない、と言ってあるのですが、それが本当なのかどうかはわかりません。
ともあれ、これから続きを読んでしまおうと思います。
2008年05月29日
『花匂う』
山本周五郎著 『花匂う』

私が初めて読んだ、山本周五郎の文庫です。
表題の「花匂う」のほか、
・「宗太兄弟の悲劇」
・「秋風不帰」
・「矢押の樋」
など11作品が収録されています。
解説含め、309ページ。新潮社刊。当時の定価360円。消費税が導入される前年ですね。
巻末に記したメモでは、1988年5月に読了しています。
書店で、たまたま目にして購入したのを、よく覚えています。当時は、山本周五郎がどんな小説を書いているのか、全く知りませんでした。
読み進めていくと、どの作品も江戸時代を舞台とした時代小説。時代小説ばかりとは思わず、途中で「あれ、もしかして全部そうなんだ」と気付いた次第です。
残念ながら、内容についてはほとんど記憶にありません。ただ、市井の町人や地方の侍を、情こまやかに描いた作品群に非常に面白味を覚え、確か、一気に読み上げたはずです。
この一冊が、私が周五郎を愛読するようになるきっかけとなりました。
私が初めて読んだ、山本周五郎の文庫です。
表題の「花匂う」のほか、
・「宗太兄弟の悲劇」
・「秋風不帰」
・「矢押の樋」
など11作品が収録されています。
解説含め、309ページ。新潮社刊。当時の定価360円。消費税が導入される前年ですね。
巻末に記したメモでは、1988年5月に読了しています。
書店で、たまたま目にして購入したのを、よく覚えています。当時は、山本周五郎がどんな小説を書いているのか、全く知りませんでした。
読み進めていくと、どの作品も江戸時代を舞台とした時代小説。時代小説ばかりとは思わず、途中で「あれ、もしかして全部そうなんだ」と気付いた次第です。
残念ながら、内容についてはほとんど記憶にありません。ただ、市井の町人や地方の侍を、情こまやかに描いた作品群に非常に面白味を覚え、確か、一気に読み上げたはずです。
この一冊が、私が周五郎を愛読するようになるきっかけとなりました。
2007年10月30日
未読本がたまっています。
最近の悩みの一つに、なかなか読書する時間がない、というのがあります。
定期購読している雑誌でさえ、ほんのちょっと読みかじっただけで次の号が送られる、ということもしばしばで、なかなか全てに目を通すことができません。
ましてや、小説その他の文庫本・単行本の読書量は、このところグッと下がっています。
理由は、仕事に費やす時間が長い、ということに尽きますが、今のところ、飢餓感はそれほどありません。
しかし、飢餓感が徐々に増して、一定のラインを超えると、一気に読書に埋没する時期を迎えるかもかもしれません。
ちょっと状況は異なりますが、学生の頃、試験前になると本を読みたくなる病(?)にかかっていました。
試験前なので、勉強以外の時間は削り、試験勉強に充てる時間を増やす、というのが普通ですよね。さりながら小生の場合、勉強のために削られる時間が何故か惜しくなって、それまではさして本も読んでいなかったくせに、無性に本を手に取りたくなるのです。現実逃避の側面も無くはなかったでしょうね。
ともあれ、当然、本を読んでいると、“この章まで読んだら勉強を始めよう”“やっぱり次の章まで”“もうひとつ先まで”・・・・・・という事態が生まれます。結果、十分な勉強をしないまま、試験に臨むことになり、成績もそれなりのものしか得られません。
まぁ、それでも落第や留年することもなく、どうにかこうにか無事卒業することはできましたけれど、もし、学生さんでこれを読んでいる方がいれば、マネはしない方がいいですよ。学力向上の面でも、また精神衛生の面でも、あまり好ましいことではありませんからね。
今、感じる飢餓感は、学生の頃のそれとは質が違い、現実から逃げるためなどということはなく、単純に娯楽としての読書への飢えですね。
ただ、怖いのは、飢えがラインを超えてきた時、波に飲まれてついつい睡眠時間を削って本を読む日が続くんじゃないかな、ということ。結構、ハマる時はハマるんですよね。
ま、人生のうちには、時にそんな一瞬があったっていいですよね! と、ちょっと強引かもしれませんが、これで納得しましょう!
*****************************************
小学校受験通信講座のアイウィッシュアカデミー
ただいま附属小学校対策講座、開講中です。
定期購読している雑誌でさえ、ほんのちょっと読みかじっただけで次の号が送られる、ということもしばしばで、なかなか全てに目を通すことができません。
ましてや、小説その他の文庫本・単行本の読書量は、このところグッと下がっています。
理由は、仕事に費やす時間が長い、ということに尽きますが、今のところ、飢餓感はそれほどありません。
しかし、飢餓感が徐々に増して、一定のラインを超えると、一気に読書に埋没する時期を迎えるかもかもしれません。
ちょっと状況は異なりますが、学生の頃、試験前になると本を読みたくなる病(?)にかかっていました。
試験前なので、勉強以外の時間は削り、試験勉強に充てる時間を増やす、というのが普通ですよね。さりながら小生の場合、勉強のために削られる時間が何故か惜しくなって、それまではさして本も読んでいなかったくせに、無性に本を手に取りたくなるのです。現実逃避の側面も無くはなかったでしょうね。
ともあれ、当然、本を読んでいると、“この章まで読んだら勉強を始めよう”“やっぱり次の章まで”“もうひとつ先まで”・・・・・・という事態が生まれます。結果、十分な勉強をしないまま、試験に臨むことになり、成績もそれなりのものしか得られません。
まぁ、それでも落第や留年することもなく、どうにかこうにか無事卒業することはできましたけれど、もし、学生さんでこれを読んでいる方がいれば、マネはしない方がいいですよ。学力向上の面でも、また精神衛生の面でも、あまり好ましいことではありませんからね。
今、感じる飢餓感は、学生の頃のそれとは質が違い、現実から逃げるためなどということはなく、単純に娯楽としての読書への飢えですね。
ただ、怖いのは、飢えがラインを超えてきた時、波に飲まれてついつい睡眠時間を削って本を読む日が続くんじゃないかな、ということ。結構、ハマる時はハマるんですよね。
ま、人生のうちには、時にそんな一瞬があったっていいですよね! と、ちょっと強引かもしれませんが、これで納得しましょう!
*****************************************
小学校受験通信講座のアイウィッシュアカデミー
ただいま附属小学校対策講座、開講中です。
2007年09月25日
可及的速やかに、って感じでいいですか?
先日、宮部みゆきさんの作品をよく読んでいた、という話をしましたが、宮部みゆきさんの作品は、文庫本で20冊から30冊ほどは持っていると思います。宮部さん以外にも、同じように10冊以上のコレクションがある作家さん、おそらく20人は下らないと思います。
このように愛好する作家さん、および、そうした作家さんの作品がmy蔵書に増えるにつれ、ちょっと困ることも起きます。
小生、ふらっと書店に出向くと、ほぼ毎回、文庫コーナーに足を運びます。そして、新刊本をざっと眺めるほか、“○○さんの本でも買おうかな”と愛読する作家さんの作品を探すこともよくあります。
そこで書棚をめぐり、目的の作家さんの作品群が並ぶ書棚にたどり着くわけですが、本のタイトルを見て、「ウ~ン」と腕組みをすること、少なくありません。
というのは、小生、読了した本のタイトル、つい忘れてしまいがちなのです。
もちろん、特に印象に残った本については、タイトルもばっちり頭に入っていますが、中にはそうではない本も時々ありまして・・・・・・。そうした本は、失礼ながら、時の流れと共に、タイトルがうっすらとフェードアウトしていったりしてます。
特に『続○○○』や『続々○○○』『続々々○○○』なんていうシリーズ化している作品群は要注意です。どこまで読んだのか定かでなくて、書店で立ち往生することしきりです。最近では、塩野七海さんの『ローマ人の物語』シリーズがそう。
今も文庫本の刊行が続いていて、確か17、8巻くらいまでは読んでいるのですが、その先どこまで購入済みかが「?」になっています。ですので、書店で同シリーズの本を見かけても、それを買っているのかいないのか、がわからず購入を見送っている状態です。
このように、割と慎重派である小生ですが、失敗はあります。
最近では今年の春。それこそ宮部みゆきさんの作品で、書店で新刊の文庫本を見つけたので、中身は確認せず、上下巻の2冊を購入しました。
“新刊なのでウチには持っていないはず”という先入観がクセ者でした。
数日後、その文庫を読んでいると、「ン!? コレ、なんか覚えがあるゾ・・・・・・」。
その本、多分10年近く前に、今回購入した出版社とは別の出版社で文庫として出されていた作品でした。
文庫の場合、たまにこのように複数の版元から刊行されることがあり、“新刊だから大丈夫だろう”と油断していると、今回のような失敗があり、「あちゃー」と落ち込みます(ちょっとですが)。
そんなこんなで、持ち数が多い作家さんについては、作品(蔵書)リストを作って持ち歩こう、とその時は考えるのですが、未だ作品リストを完成して陽の目を見たことはございません。
何故かと申しますと、作品リストを作るには、まずあちこちに散らばる文庫本を集め、書棚を整理し、すべて作家順に並べないといけないじゃないですか。生来無精者の小生。なかなか重い腰が上がらないんですよねぇ・・・・・・。
まぁ。作品リストが無くっても、小生が本の内容を覚えていればダブって購入することは無いんですけどね・・・・・・でも、そっちも最近は怪しいし、やっぱりリストを作るべきかも。
よし、これを機会にやってみるかな。ウン、やってみるかぁ。
ということで、結果は、また報告します(いつになるかはわかりませんけれど)。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。
このように愛好する作家さん、および、そうした作家さんの作品がmy蔵書に増えるにつれ、ちょっと困ることも起きます。
小生、ふらっと書店に出向くと、ほぼ毎回、文庫コーナーに足を運びます。そして、新刊本をざっと眺めるほか、“○○さんの本でも買おうかな”と愛読する作家さんの作品を探すこともよくあります。
そこで書棚をめぐり、目的の作家さんの作品群が並ぶ書棚にたどり着くわけですが、本のタイトルを見て、「ウ~ン」と腕組みをすること、少なくありません。
というのは、小生、読了した本のタイトル、つい忘れてしまいがちなのです。
もちろん、特に印象に残った本については、タイトルもばっちり頭に入っていますが、中にはそうではない本も時々ありまして・・・・・・。そうした本は、失礼ながら、時の流れと共に、タイトルがうっすらとフェードアウトしていったりしてます。
特に『続○○○』や『続々○○○』『続々々○○○』なんていうシリーズ化している作品群は要注意です。どこまで読んだのか定かでなくて、書店で立ち往生することしきりです。最近では、塩野七海さんの『ローマ人の物語』シリーズがそう。
今も文庫本の刊行が続いていて、確か17、8巻くらいまでは読んでいるのですが、その先どこまで購入済みかが「?」になっています。ですので、書店で同シリーズの本を見かけても、それを買っているのかいないのか、がわからず購入を見送っている状態です。
このように、割と慎重派である小生ですが、失敗はあります。
最近では今年の春。それこそ宮部みゆきさんの作品で、書店で新刊の文庫本を見つけたので、中身は確認せず、上下巻の2冊を購入しました。
“新刊なのでウチには持っていないはず”という先入観がクセ者でした。
数日後、その文庫を読んでいると、「ン!? コレ、なんか覚えがあるゾ・・・・・・」。
その本、多分10年近く前に、今回購入した出版社とは別の出版社で文庫として出されていた作品でした。
文庫の場合、たまにこのように複数の版元から刊行されることがあり、“新刊だから大丈夫だろう”と油断していると、今回のような失敗があり、「あちゃー」と落ち込みます(ちょっとですが)。
そんなこんなで、持ち数が多い作家さんについては、作品(蔵書)リストを作って持ち歩こう、とその時は考えるのですが、未だ作品リストを完成して陽の目を見たことはございません。
何故かと申しますと、作品リストを作るには、まずあちこちに散らばる文庫本を集め、書棚を整理し、すべて作家順に並べないといけないじゃないですか。生来無精者の小生。なかなか重い腰が上がらないんですよねぇ・・・・・・。
まぁ。作品リストが無くっても、小生が本の内容を覚えていればダブって購入することは無いんですけどね・・・・・・でも、そっちも最近は怪しいし、やっぱりリストを作るべきかも。
よし、これを機会にやってみるかな。ウン、やってみるかぁ。
ということで、結果は、また報告します(いつになるかはわかりませんけれど)。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。
2007年09月20日
みゆき(その1)
皆様、こんばんは。マンボウくんでございます。

本日は久しぶりに(単にネタがなかったからですが)、愛読書シリーズの第4弾と致します。
確か、前回は就職前年の、読書に耽溺していた頃の話でしたね。
さて、その後、就職して一人暮らしを始めた小生。仕事が忙しくてなかなか読書にかける時間もなく、読了する冊数も激減。就職前年の130冊余りから、年間20~50冊程度の読了数となりました。
社会人になって間もない頃からよく読みだしたのが、宮部みゆきさん。ちょうど宮部さんが売れ始めてきた頃と重なっていたと思います。確か、初めて読んだのは『レベル7』。長編ミステリーですが、引き込まれてすぐに読み終えたのを覚えています。まだその頃は宮部さんも若手と言ってよいお年頃だったはずですが、その筆力に感服しましたね。
続いて『魔術はささやく』『我らが隣人の犯罪』『龍は眠る』など、それまでに刊行されていた本を続けざまに読みました。いずれも、とても読み応えがあり、一言で言って“おもしろい”作品ばかりでした。
宮部さんの恐るべき(?)点は、ミステリーという1つのジャンルにとどまらず、時代物やファンタジー・SF・ほんわか物(ちょっとほんわかする作品のことね)など幅広い分野の作品を発表していること、そしてそのいずれの分野の作品も秀作揃いであることです。おそらくは才能豊かであり、努力家でもあるのでしょう。自身を振り返ってみても、うらやましい限りです。
さて、代表作とも言うべき作品がいくつもある宮部さんの小説の中でも、個人的に“コレ”として挙げるのは『火車』。
あらすじは省きますが、カード社会の覆面性に焦点を当てた社会派ミステリーと言ってよいのでしょうか、ともかく考察に考察を重ねて執筆されたであろうことが推察される、深みのある作品です。ちなみに、この作品で宮部さんは新潮社主催の山本周五郎賞を受賞なさっています。
『火車』に限らず、宮部作品はいずれも期待を裏切らない小説ばかり(と小生は思います)ので、おひとつお手にとってみられるのもよいのではないでしょうか。
ではでは、また。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。

本日は久しぶりに(単にネタがなかったからですが)、愛読書シリーズの第4弾と致します。
確か、前回は就職前年の、読書に耽溺していた頃の話でしたね。
さて、その後、就職して一人暮らしを始めた小生。仕事が忙しくてなかなか読書にかける時間もなく、読了する冊数も激減。就職前年の130冊余りから、年間20~50冊程度の読了数となりました。
社会人になって間もない頃からよく読みだしたのが、宮部みゆきさん。ちょうど宮部さんが売れ始めてきた頃と重なっていたと思います。確か、初めて読んだのは『レベル7』。長編ミステリーですが、引き込まれてすぐに読み終えたのを覚えています。まだその頃は宮部さんも若手と言ってよいお年頃だったはずですが、その筆力に感服しましたね。
続いて『魔術はささやく』『我らが隣人の犯罪』『龍は眠る』など、それまでに刊行されていた本を続けざまに読みました。いずれも、とても読み応えがあり、一言で言って“おもしろい”作品ばかりでした。
宮部さんの恐るべき(?)点は、ミステリーという1つのジャンルにとどまらず、時代物やファンタジー・SF・ほんわか物(ちょっとほんわかする作品のことね)など幅広い分野の作品を発表していること、そしてそのいずれの分野の作品も秀作揃いであることです。おそらくは才能豊かであり、努力家でもあるのでしょう。自身を振り返ってみても、うらやましい限りです。
さて、代表作とも言うべき作品がいくつもある宮部さんの小説の中でも、個人的に“コレ”として挙げるのは『火車』。
あらすじは省きますが、カード社会の覆面性に焦点を当てた社会派ミステリーと言ってよいのでしょうか、ともかく考察に考察を重ねて執筆されたであろうことが推察される、深みのある作品です。ちなみに、この作品で宮部さんは新潮社主催の山本周五郎賞を受賞なさっています。
『火車』に限らず、宮部作品はいずれも期待を裏切らない小説ばかり(と小生は思います)ので、おひとつお手にとってみられるのもよいのではないでしょうか。
ではでは、また。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。
2007年09月20日
自宅の棚も溢れています。
本日の書き下ろしの前に、当社HPの8月28日の日記の分を転載させてください。
それから、書き下ろしを載せます。
---------
以下は当社HPの8月28日の日記からの転載です。
ここにブログを開設する前の日の日記ですね。
==============================
本日はよいネタが浮かびませんので、困ったときのシリーズもの、ということで、久々の愛読書コーナー第3弾です。
さて、前回は大学の前半頃までだったと思いますが、その後、就職する前の約1年間、小生の人生の中で最も読書に耽溺する時代を迎えます。
きっかけとなった1冊は、芥川賞作家である宮本輝氏の『錦繍』。内容は省略しますが、往復書簡の形で綴られる文体が、繊細な情感を描き出し、引き込まれるように読んだことを覚えています。
実はそれまで、現代作家の小説を読むことはほとんどありませんでした。特に理由があったわけではありませんが、当時の小生、小説と言うと、漱石だの芥川だの、ある程度評価の定まった、教科書にもその名が出てくるような作家のものを読むべし、といった固定観念に縛られていたような気もします。
そこでたまたま読んだ『錦繍』で、カルチャーショックを受けたのです。「現代作家も読んでみよう」というスイッチが入り、堰を切ったように、書店に行ってはいろんな作家の作品を手にするようになりました。
それまで現代作家さんはあまり知らなかったので、毎月の文庫の新刊を何冊か買い、面白いと感じた作家の作品をまた探して読む、というパターンでした。
書棚にどんどん本がたまっていき、それを作家ごとに整理するのも楽しんでいましたね。当時、冊数が多かったのは、まず宮本輝氏。宮本氏の作品は『青が散る』『避暑地の猫』など、当時文庫化されていたものはほとんど読了しました。宮本輝さんには“ハマった”と言えるでしょうね。その他、連城三紀彦氏・渡辺淳一氏・佐藤正午氏なども愛読しました。
ちなみに、佐藤正午さんに関しては、それから10年ばかりご無沙汰していたあと、世紀が代わった頃にまた数冊続けて読みました。以前のような荒々しさはありませんでしたが、奥行きのある文章に、(僭越ですが)作家としての成長を感じました。中でも“岐路”がテーマとなる『ジャンプ』は、(語彙が貧弱で申し訳ありませんが)非常に秀逸な出来である、と個人的に同氏の代表作に推させていただいております。
この他にも、山本周五郎氏・池波正太郎氏といった、時代小説にもはまりました。両氏の本は、小生の文庫コレクションでも、その数において1位と2位を競うほどです。一緒に取り上げると混同されてしまいそうですが、両氏の作風は全く別です。池波正太郎さんは『鬼平』シリーズや『剣客商売』シリーズで知られるように、エンタテインメント性の強い作風で、純粋に“面白く”読んでいくことができますね。
一方、同じ時代物でも山本周五郎さんの作品は、武家物にして市井物にしても、人の情が表に出る作風と言えるのではないでしょうか。また、緻密な考証で歴史解釈にも一石を投じた『樅の木は残った』を読んだ際は、「考察することに限界はないんだ」と感嘆したというか、白旗を揚げましたね。こりゃあ、すごいわ、と。
と、そんな具合で、特定作家の作品も読み集めつつ、できるだけ幅広く本を手にしたあの1年。就職で地元を離れるまでにおよそ130冊以上読了しました。読了数ならばもっと上をいく方も多数いらっしゃると思いますが、当時の小生としては、時間があれば本を読んでいたという記憶があります。おそらく、中学生以後のそれまでに読んだ冊数より、この1年間で読んだ数の方がずっと多かったのではないでしょうか。言わば小生の読書狂時代でした。
今振り返っても、あの頃はホントよく読んだよなぁ、と感慨深い思いで胸が満ちます。就職後はさすがに読書量は落ちましたが、あの頃の経験があるせいか、趣味欄には今でも、“読書”と臆することなく書くことができます。昔取った杵柄、ってやつかもしれませんけど。
ということで、本日はおしまいです。
あまりにフツーな内容で、オチがないのが、小生としてはおちっがない、おちっかない、おちつかない、落ち着かない、気分です・・・・・・。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。
それから、書き下ろしを載せます。
---------
以下は当社HPの8月28日の日記からの転載です。
ここにブログを開設する前の日の日記ですね。
==============================
本日はよいネタが浮かびませんので、困ったときのシリーズもの、ということで、久々の愛読書コーナー第3弾です。
さて、前回は大学の前半頃までだったと思いますが、その後、就職する前の約1年間、小生の人生の中で最も読書に耽溺する時代を迎えます。
きっかけとなった1冊は、芥川賞作家である宮本輝氏の『錦繍』。内容は省略しますが、往復書簡の形で綴られる文体が、繊細な情感を描き出し、引き込まれるように読んだことを覚えています。
実はそれまで、現代作家の小説を読むことはほとんどありませんでした。特に理由があったわけではありませんが、当時の小生、小説と言うと、漱石だの芥川だの、ある程度評価の定まった、教科書にもその名が出てくるような作家のものを読むべし、といった固定観念に縛られていたような気もします。
そこでたまたま読んだ『錦繍』で、カルチャーショックを受けたのです。「現代作家も読んでみよう」というスイッチが入り、堰を切ったように、書店に行ってはいろんな作家の作品を手にするようになりました。
それまで現代作家さんはあまり知らなかったので、毎月の文庫の新刊を何冊か買い、面白いと感じた作家の作品をまた探して読む、というパターンでした。
書棚にどんどん本がたまっていき、それを作家ごとに整理するのも楽しんでいましたね。当時、冊数が多かったのは、まず宮本輝氏。宮本氏の作品は『青が散る』『避暑地の猫』など、当時文庫化されていたものはほとんど読了しました。宮本輝さんには“ハマった”と言えるでしょうね。その他、連城三紀彦氏・渡辺淳一氏・佐藤正午氏なども愛読しました。
ちなみに、佐藤正午さんに関しては、それから10年ばかりご無沙汰していたあと、世紀が代わった頃にまた数冊続けて読みました。以前のような荒々しさはありませんでしたが、奥行きのある文章に、(僭越ですが)作家としての成長を感じました。中でも“岐路”がテーマとなる『ジャンプ』は、(語彙が貧弱で申し訳ありませんが)非常に秀逸な出来である、と個人的に同氏の代表作に推させていただいております。
この他にも、山本周五郎氏・池波正太郎氏といった、時代小説にもはまりました。両氏の本は、小生の文庫コレクションでも、その数において1位と2位を競うほどです。一緒に取り上げると混同されてしまいそうですが、両氏の作風は全く別です。池波正太郎さんは『鬼平』シリーズや『剣客商売』シリーズで知られるように、エンタテインメント性の強い作風で、純粋に“面白く”読んでいくことができますね。
一方、同じ時代物でも山本周五郎さんの作品は、武家物にして市井物にしても、人の情が表に出る作風と言えるのではないでしょうか。また、緻密な考証で歴史解釈にも一石を投じた『樅の木は残った』を読んだ際は、「考察することに限界はないんだ」と感嘆したというか、白旗を揚げましたね。こりゃあ、すごいわ、と。
と、そんな具合で、特定作家の作品も読み集めつつ、できるだけ幅広く本を手にしたあの1年。就職で地元を離れるまでにおよそ130冊以上読了しました。読了数ならばもっと上をいく方も多数いらっしゃると思いますが、当時の小生としては、時間があれば本を読んでいたという記憶があります。おそらく、中学生以後のそれまでに読んだ冊数より、この1年間で読んだ数の方がずっと多かったのではないでしょうか。言わば小生の読書狂時代でした。
今振り返っても、あの頃はホントよく読んだよなぁ、と感慨深い思いで胸が満ちます。就職後はさすがに読書量は落ちましたが、あの頃の経験があるせいか、趣味欄には今でも、“読書”と臆することなく書くことができます。昔取った杵柄、ってやつかもしれませんけど。
ということで、本日はおしまいです。
あまりにフツーな内容で、オチがないのが、小生としてはおちっがない、おちっかない、おちつかない、落ち着かない、気分です・・・・・・。
*****************************************
アイウィッシュアカデミーのHPの
“マンボウくんのひとりごと”には、当ブログ掲載前の7月からの
日記があります。
お時間あればお立ち寄りください。




